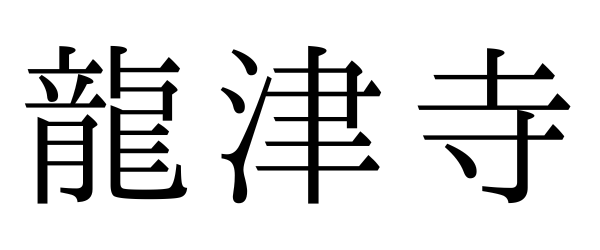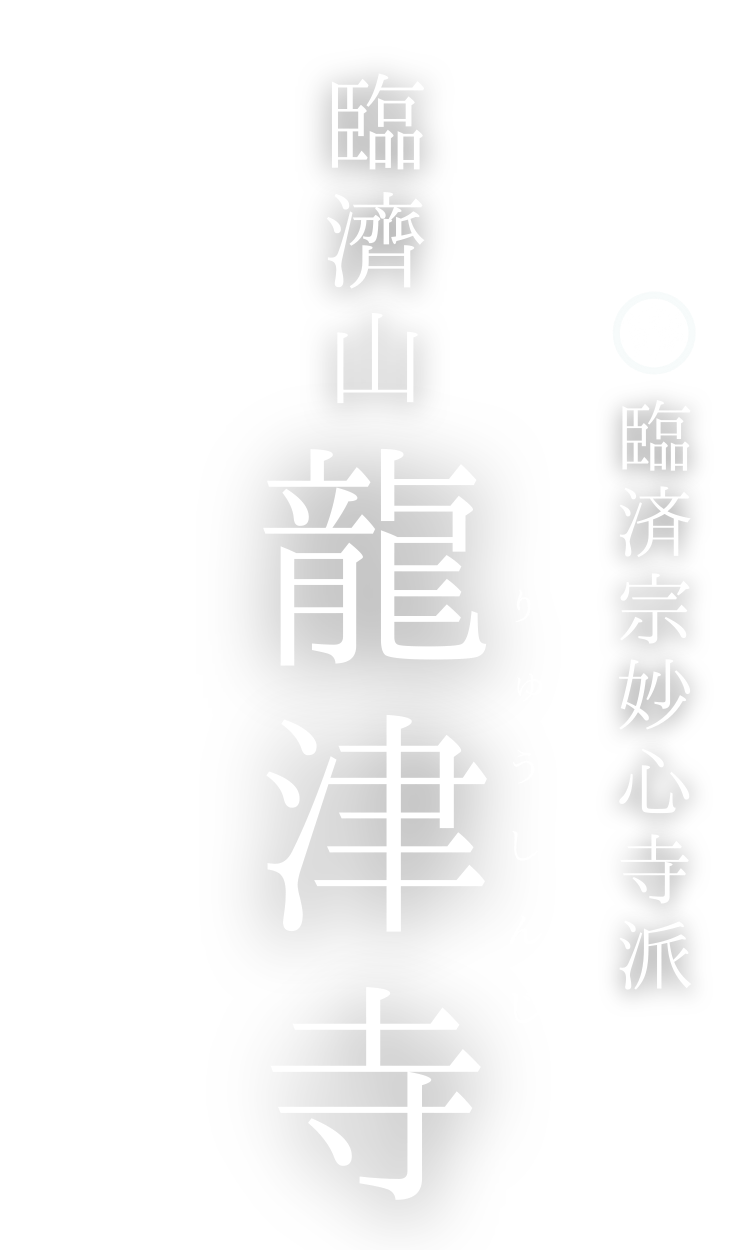寺院縁起

臨済宗妙心寺派 龍津寺
当山は臨済宗妙心寺派の寺院です。
その創建は明らかではないが、残された史料によれば、慶長13年(1608)に藤堂高虎公が津の城主となって、伊予(愛媛県)の高僧、乾峯和尚を拝請して住職としたのです。
その後、正保4年(1647)には大伽藍が完成して、十有余カ寺の末寺を持つ中本山の寺格となりました。
その後も代々勅任の和尚が住職となり、京都の大本山妙心寺管長に選任される名僧が輩出するなどして、全国より雲水が多数参集し、教義の宣揚と禅の修養道場となり、また城下随一の武士の子弟や庶民の学山となりました。また歴代藩主の帰依崇敬極めて篤く、特に天明の頃に住職された第6世径山和尚は約7万坪の広大な寺域に、七堂伽藍を完成し、その名声は四海に轟いたといわれております。
その後も幾多の改修をしながら法燈を繋いでおり、幸いにもその後の太平洋戦争の戦火をも免れて、昭和27年(1952)には本堂の仏間を修理し、ほぼ現在の伽藍配置となったのです。
現在の本堂の資材は安永6年(1777)のもので、約240年前の物です。現存する梵鐘は径山和尚時代のものです。他境内には、山溪地蔵尊、延命地蔵尊、納骨永代供養塔に寂光地蔵尊が安置されています。令和元年には諸堂の改築改修を完了しております。
住職の想い
時を慈しみ、人を思う
物事の選択肢が多様し、供養の在り方も大きく移り変わっているものの、過ぎし日を慈しみ、人を偲び、想う気持ちは、時代がどうあれ変わらないものです。
歴史ある地域の寺院としての役割を受け継ぎながら、生きている人の想いに寄り添うべく、様々なご相談に応え、多様な声に向かい合っていきます。
これまでも、これからもずっと。
多様な声に応え、常に人に寄り添ってゆく
これから私たち住職、宗教者がなすべきことは、一人ひとりのお話に耳を傾け、特にお墓のことや供養についての悩みに対応していくことです。かつては先祖代々のお墓があり、仏壇があって供養をすることが当然でしたが、少子化、核家族化、家の後継がいないなど、様々な社会変化が起こってきたことにより、家が中心だった供養のあり方が、個人に変わってきたように思われます。
龍津寺では、時代の変化の中で、少しでも皆さまのお手伝いができればと考えています。この先、供養をどうしていけばいいのか、ご本人様の状況や立場をしっかりお聞きし、親身になってご相談に対応させていただくことがいちばんだと思います。お寺の発展ではなく、皆さまに寄り添い、お釈迦様の教えを伝えていけたらといつも感じております。
臨済宗妙心寺派
龍津寺 住職 村山光彦
住職プロフィール
寺に生まれ、4歳より法要佛事に携わり、禅宗の専門大学を卒業し、その後禅の専門道場にて修業。
本山京都花園妙心寺にて、18年奉職し現住となる。
| 寺院概要 | |
|---|---|
| 寺院名 | 龍津寺(りゅうしんじ) |
| 宗派 | 臨済宗妙心寺派 |
| 住所 | 〒514-0037 三重県津市東古河町8-24 google map |
| 電話番号 | 059-228-6550 |
| HP | https://ryushinji.com/ |
| 交通案内 | 電車の場合 近鉄名古屋線 津新町駅:徒歩約10分 お車の場合 伊勢自動車道 津IC:出口より車で約5分 |
| 年中行事 | |
|---|---|
| 1月 | 修正会 元旦に厳修されます『歳(さい)旦(たん)大般若(だいはんにゃ)修正会(しゅしょうえ)』とは、新しい年の始め(歳旦)に、み佛の教えを守り、自らの歩みを正し、修していこうという誓いを込めてつとめる法要です。 中国では一月を正とし、この法会を修したので修正会(しゅしょうえ)と呼ぶようになりました。 年の暮れに除夜の鐘をついて、煩悩を払い落として正月を迎え、自らの生き方を正し、み佛の教えのままに精進することを、ご本尊様・ご先祖様にお誓いしましょう。 |
| 3月 | 春彼岸 |
| 5月 | 降誕会(はなまつり) 「釋尊(しゃくそん)降誕会(ごうたんえ)」(お釋迦さまの誕生日)は灌仏会(かんぶつえ)または仏生会(ぶっしょうえ)といわれており、一般には「花まつり」といわれております。お釋迦さまは、今から二千五百年ほど前の旧暦4月8日に、ルンビニー園という花園でお生まれになりました。そして「天上(てんじょう)天下(てんげ)唯我独尊(ゆいがどくそん)」のおことばを発せられたといわれております。 法要では、花(はな)御堂(みどう)をおまつりし、甘茶(あまちゃ)をかけて、その尊い「み教え」をお示しくださったお釋迦様のご誕生を祝います。そして同時に、私たちが「いま生かされている」喜びと、この世に「いのちを頂いた」喜びを、ご先祖様に感謝する供養を行います。 |
| 7月 | 七月盆 |
| 8月 | 八月盆(盆総供養) |
| 9月 | 秋彼岸 |
| 12月 | 成道会 「釈尊成道会(じょうどうえ)」は、人間として生まれ、その幸福について悩み続けられたお釈迦さまが、難行苦行ののち菩提樹のもと七日七晩ひたすら坐禅をされ、ついに八日目の早暁にお悟りをひらかれた日を記念して行われる法会です。 除夜の鐘 |